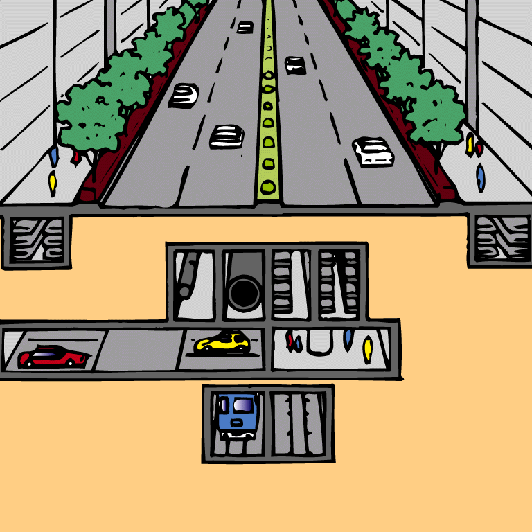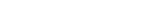推進工事とは
都市を中心とする生活圏には、下水道、水道、ガス、電力、通信等のライフラインがあり、その多くは地中に管渠(かんきょ)として埋設されています。
管渠(かんきょ)の埋設方法
これらの管渠の埋設方法には、開削工法と非開削工法があります。
開削工法
開削工法では、名前のとおり工事箇所の地面を必要な深さまで掘削(開削)して、その底面に既製の管やボックスカルバートなどを敷設して埋め戻します。
非開削法では、工事箇所の両端に発進立坑と到達立坑と呼ばれる縦穴を掘削し、発進立坑から地中を掘削するための機械(掘削機)を使用して土を削っていきます。削られた土は、パイプなどを使用して地上に運ばれます。
このように、非開削工法は開削工法に比べて地上面を堀ることが少なくなるため、工事占用面積の減少、騒音、振動、粉じん等の工事公害の低減がはかれ、交通や市民生活への影響を低減できるため、都市環境対策に優れています。
非開削工法
非開削工法には、推進工法とシールド工法があります。推進工法とシールド工法との大きな違いはシールド工法は掘削機を油圧ジャッキによって直接前進させて、掘られたトンネル内で、セグメント(枠)を組み立てるのに対して、推進工法では、推進管と呼ばれる円筒状の管を推進機と一緒に発進立坑に設置された油圧ジャッキで前進させるということです。
内部でセグメントを組み立てる必要がないため、シールド工法より小さい管径の工事を行うことができます。
推進工法
推進工法で行う工事のことを推進工事と呼ぶ事があります。
日本の工事では、1948年に軌道下を内径600mmの鋳鉄管をさや管としての施工で最初に使用されました。
当初の推進工法は特殊工法としてガス、水道、通信ケーブル等さや管の軌道や道路の横断布設を対象としていましたが、需要の拡大に伴って、シールド工法などの技術を取り入れて、安全性の高い工法へと進展し、泥水式推進工法や土圧式推進工法といった機械式推進工法が開発されました。
推進工法では、立坑の油圧ジャッキの力で掘進するため、複雑な線形や長距離の掘削には不向きでしたが、大都市から地方中小都市へあるいは幹線から準幹線や枝線へと下水道整備の拡大に伴って、的要求に応じて、複数急曲線施工の確立、資器材などの改良などや、多種の工法が推進工事をされる各社で研究、開発され、それに伴って1,000m以上の推進も可能になっています。